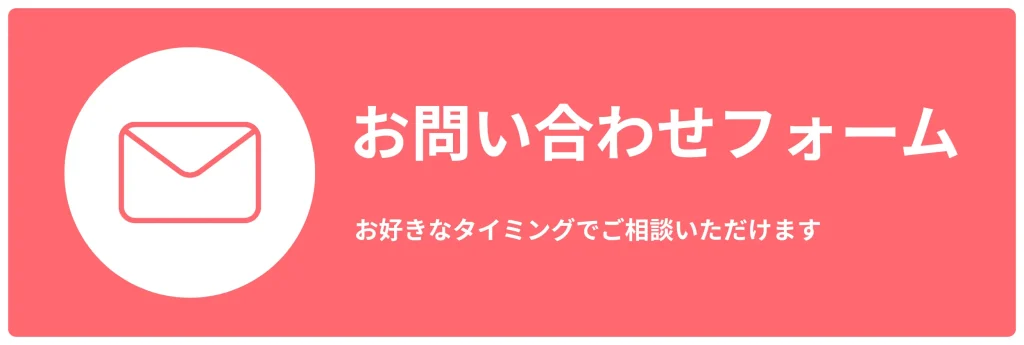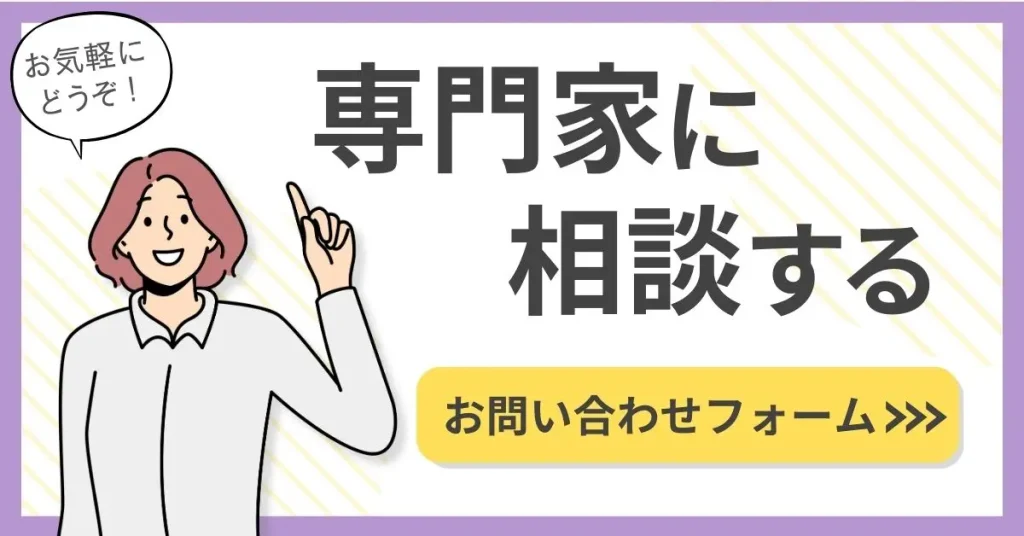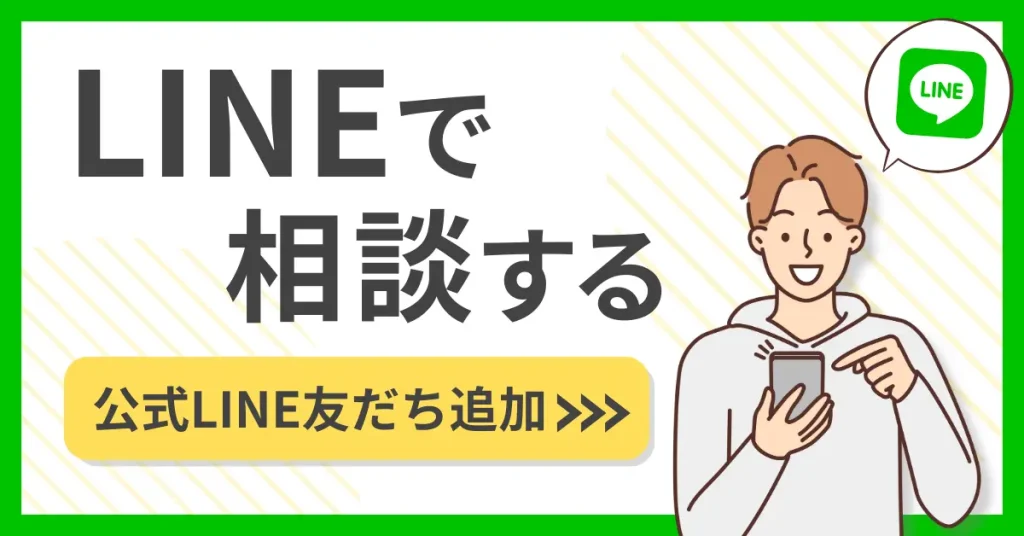「何度も話しかけているのに返事をしない」「質問と違う答えが返ってくる」「家族みんなで話しをしていても、常にボーっとしている」・・・。高齢のご家族にこのようなお悩みをお持ちではありませんか?当店にも「聞こえにくい親の対応に困っている」という声はよく寄せられています。今回は、そんな「聞こえにくい親にイライラする」という場合に、お互いが気持ちよく過ごせるためのヒントをご紹介します。聞こえにくい家族とのコミュニケーションにお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
\聞こえのお悩みはうぐいす補聴器へご相談ください/
「テレビの音が大きいと言われた」「インターホンや家族の呼びかけに気付かなかった」
そんなご経験はありませんか?
実はそれ、年齢とともに聞こえが悪くなっていく加齢性難聴かもしれません。
加齢性難聴は、老眼やお顔のシワなどと同様に、年齢を重ねると誰でも起こりうるもの。
適切なケアで日々の生活をぐんとラクにすることができます。
詳しくは、下記よりお問い合わせください。

【この記事の監修者】
田中智子(認定補聴器技能者・うぐいす補聴器 代表取締役)
補聴器を「日常生活をポジティブに自分らしく過ごせるようになるためのツール」と捉え、補聴器専門店「うぐいす補聴器」を開業。以前は有名補聴器メーカーのマーケティング部に所属し、全国5000店舗へ補聴器販売の指導を実施した経歴を持つ。高齢者難聴を得意とし、地域住民への啓蒙活動、高齢者への補聴器の装用トレーニングなども実施している。
__
目次
高齢の親の耳が遠くて イライラ…知恵袋などでも質問の多いトピック

- 話しかけても毎回必ず1度は「えっ?」と言われる。外だと雑音もあるせいか 2 、3度聞き直されることが頻繁にある
- すべての言葉に対して「え?」と反応してくるのが最近少しストレス
- ふとした会話も気を遣わなければいけなくてイライラしてしまう
これらは、日常のあらゆる疑問を質問したり回答したりできるサイト「Yahoo!知恵袋」で見かけた、聞こえにくい親に対するお悩み投稿の一文です。多くの人が「耳の遠くなった親」に対してイラ立ってしまったり、戸惑ったりしているようです。

聞こえづらいご家族がいらっしゃると、周りの方はそのぶん大きな声で話さないといけません。大きな声を出すということは、通常よりも物理的にエネルギーを消耗しますから、その状態が続くことでストレスや疲労感がたまってしまうのは無理もありません。自分の親にイライラしてしまったとしても、ご自分を責める必要はないのです。
昔は正常値だったのに・・・加齢と難聴の関係性

仕事をしていた現役時代、健康診断で聴力検査に引っかかった経験はない、という人も多いのではないでしょうか。
しかし、加齢性の難聴は年齢を重ねるのとともに徐々に進行するため、自分では聞こえにくくなっていることに気づかないことがあります。知らず知らずのうちに難聴が進行し、いつの間にかテレビの音が大きくなっていたり、体温計の音に気づいていなかったりと「耳が遠い状態」になってしまっていることもあるのです。これをそのままにしておくと、日常会話でも聞き返すことが増えたり、たびたび聞き間違えたりするなど、不便が目立ってくるかもしれません。
加齢性難聴は一度悪くなったら戻せない
加齢性の難聴の場合、残念ながら一度悪くなってしまうと元に戻すことができません。
ですので、早い段階から介入し進行を食い止めるか、もしくは、すでに聞こえにくくなっているのであれば、どれだけ早めに対処するかが、とても大切な分かれ道になってくるのです。
聞こえにくさ、放置していませんか?
若い頃に比べて耳が遠くなった気がする・・・
そんな風に感じたら、ぜひ一度当店にご相談ください。
老眼になればメガネを着けるように、聞こえにくくなったら補聴器を使うのがおすすめです。
正しくケアすることで、聞こえにくさのストレスを大幅に軽減できるかもしれません。
「耳が聞こえにくくなること」はひとつの老化現象

加齢にともない耳が聞こえにくくなることは、ごく自然なこと。
老眼や白髪が増えるといった現象と同じように、難聴も加齢によって起こる老化現象の一つです。耳だけではなく「腰痛がひどくて・・・」「最近目が見えづらいわ・・」というように、不調が出てくる箇所はさまざま。何十年も使った身体ですから、どこかしらにガタがくるのは当然のことでもあります。
難聴を含めた加齢現象は、年齢を重ねれば誰にでも起こりうる当たり前の現象です。ですので、そのこと自体を悲観する必要はありませんし、出てきた症状は、その都度適切に対処すれば良いのです。
高い音が聞こえにくい!高音から聞こえなくなるのはなぜ?

難聴は、蝸牛(耳の奥にある器官)にある有毛細胞が傷つくことで起こるといわれています。
有毛細胞は、その位置する場所によって分析する音の高さが違います。蝸牛の入口付近にある有毛細胞は高い音を分析、奥に行くほど低い音を分析します。入口に近い有毛細胞ほど多くの音にさらされるため、一番ダメージを受けやすいです。それが結果的に高い音が先に聞こえにくくなるという現象を引き起こすのです。
「お年寄りの耳が遠くなるのは仕方がないから何もしない」は昔のこと

「歳だから仕方ない」そんな考えはもう昔のものです。
最近では、難聴を放置すると脳へ悪影響を与えることもわかってきていて、難聴へ適切な対処を行うことが推奨されはじめました。
音を聞いているのは、正確には耳ではなく「脳」。

耳から入った音声情報は脳が電気信号としてとらえ、音として認識します。しかし、耳が遠くなったことによって脳に音の刺激がいかなくなると、脳の活動がどんどん弱まり、結果的に脳が委縮したり、変性が起こるなど、大きな問題となってしまうのです。
そのため、「もう歳だから」と放置せず、早めの対処が重要です。聞こえが改善することで、社会参加などへの意欲も高まり、イキイキと過ごせる時間が増えるのではないでしょうか。
耳が遠い家族へできるサポート

年齢を重ねるにつれて聞こえにくくなるのは当然の現象。でもだからといって、家族がストレスやイライラを抱えたままでは、負担は増えるばかりです。お互いが気持ちよく過ごすためには、家族のサポートは必要不可欠です。聞こえづらい家族のためにできることは、次のようなサポートがあります。
サポート① テレビ用スピーカーを導入する

難聴の方は知らず知らずのうちに、テレビの音量が大きくなりがち。家族間で快適なテレビの音量が異なると、「一緒にテレビを見たくない」「テレビがついているからリビングに行くのをやめよう」などと、家族だんらんの機会が失われてしまう可能性もあります。そんなときには、テレビ用スピーカーを導入するのがおすすめです。手元に置いて音量調整ができるスピーカーなので、テレビの音量を上げずに聞こえにくい人だけ大きい音で聞くことができます。
こういったスピーカーは電機量販店などでも気軽に購入できますので、テレビの音量に悩まれている方はぜひ一度お試しください。
サポート② 補聴器の購入を検討する
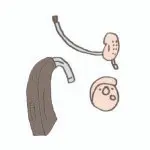
脳に刺激を与えて今の聴力を維持するためにも、早めの補聴器装用をおすすめします。聞こえない期間が長くなればなるほど、補聴器に慣れることにも時間がかかり、結局補聴器をつけるのを習慣化できない、といったことにも繋がりかねません。聞こえにくさを感じるようになったら、できるだけ早く対処しましょう。
なかには、補聴器をつけることに対して「老化の象徴のようだ」と、抵抗感を示す方もいらっしゃいます。しかし現在は、補聴器に見えないようなスタイリッシュな機種も増えてきています。多くの補聴器専門店では補聴器の試聴が可能ですので、気軽な気持ちで一度試してみてはいかがでしょうか。
サポート③ 聞き取りやすい話し方を意識する
難聴の人が日常を快適に過ごすには、ご家族をはじめとする周りの人のサポートが必要不可欠です。耳が聞こえにくい人と会話するときは、ぜひ次のような事に注意してみてください。
| 難聴者への話し方や配慮 | 詳細 |
|---|---|
| ①耳元ではなく、正面から話す | 耳が遠いからと、耳元に寄って大きな声で話すことは逆効果の場合があります。正面で口元を見せながら、ゆっくり・はっきりと会話をしましょう。 |
| ②文字ごとではなく、文節ごとで区切る | ゆっくり話してくださいというと、「わ」「た」「し」「は」のように、1文字1文字で区切って話される人もいらっしゃいます。しかし1文字ずつではなく、「わたしは」のように、文節ごとで区切ってゆっくりとお話しするほうが伝わりやすいです。 |
| ③話しかけるときは肩や手に触れる、話題が変わるときは合図をする、などの配慮 | 少しの工夫で、話しかける側も話しかけられる側も大幅にストレスを軽減できます。話しかけるときに合図をしたり、話題が変わるときにしっかりと伝えると、話を聞く方も安心して聞くことができます。小さな配慮ですが、心がけてみてください。 |
| ④音が聞こえることと言葉が聞き取れることは違うことを理解 | 補聴器を使用していると「補聴器を使ってるなら聞こえるでしょ」と誤解されてしまいがち。難聴の状態によっては、補聴器を使っても言葉の聞き取りまでは難しいという人が居ます。他にも、補聴器を使い始めたばかりの人なら、補聴器の音に慣れるまでには時間がかかるでしょう。補聴器を使っているからといって、会話にサポートが必要ないわけではありません。 |
うちの親に補聴器は必要?聞こえのことなら当店へご相談ください
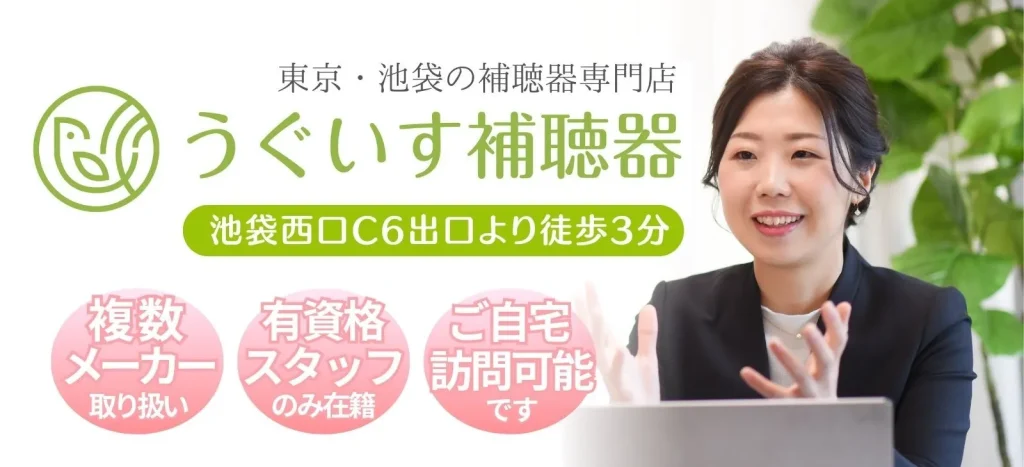
東京・池袋の補聴器専門店「うぐいす補聴器」では、聞こえにお悩みのご本人はもちろん、ご家族などからのご相談にも対応しております。また当店に在籍するスタッフは、全員が認定補聴器技能者または言語聴覚士の資格を有する「聞こえの専門家」。おひとりおひとりのお悩みに合わせて高度なご提案をいたします。小さなことでも、ぜひお気軽にご相談ください。
お電話 050-3590-5913
(日・月は定休日です)